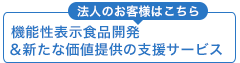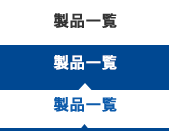森下仁丹百年物語
第1章 黎明期
創業者紹介 - 大阪での丁稚奉公時代
創業者・森下博は、1869年(明治2年)11月3日、広島県沼隈郡鞆町(ぬまくまぐんともちょう)(現・福山市)で、佐野右衛門・佐和子の長男として生まれた。幼名は茂三。
博の祖父は鞆の「撫屋(なでや)」号森下家12代茂右衛門の3男であったが、鞆の由緒ある沼名前(ぬなくま)神社(祇園神社)の宮司・大宮家に婿養子に入った。そして大宮家の長女・京子との間に生まれたのが、博の父である。博が生まれた頃は、父も祖父とともに沼名前神社の宮司の職にあった。
博が物心つく頃、祖父の出身である森下家に世継ぎが絶えたことから、祖父は博一家を連れて森下家に戻り、博の父・佐野右衛門に森下家14代を継がせた。
森下家に戻った佐野右衛門は、神職から一転して煙草の製造販売の道に入ったが、いわゆる士族の商法でうまくはいかなかった。そのため、長男には学問よりも実地の仕事に慣れさせた方が将来のためになると判断して、博が9歳の年に学校をやめさせ、備後府中在宮内村の煙草商「角新」に見習奉公に出した。「角新」の夫婦は、自分の子供のように博を可愛がり、博はここで12歳まで、煙草の栽培から製造はもちろん田植え、草とり、牛をひくことまで一通り学んだのである。
見習奉公の年季があけた博は、鞆町出身で備後府中の小学校に赴任していた分部坦という先生に引き取られて再び勉学の道に戻り、分部先生から福沢諭吉の「学問のすゝめ」や「世界国尽」を学んだのだった。しかし、翌年、父の病気のために鞆の両親の許に呼び戻され、再び学業を諦めたのである。
1882年(明治15年)5月8日、父・佐野右衛門が亡くなると、博は家督を相続して森下家15代佐野右衛門を襲名。しかし、福沢諭吉の著作で知った新しい時代や未知の世界への夢は忘れがたく、3回忌をすませた15歳の年に単身大阪へとのぼり、大阪で医者を開業していた叔父・沢田吾一の許に身を寄せた。ここで博は、沢田の知人・桑田墨荘の紹介によって心斎橋の舶来小間物問屋「三木元洋品店」に丁稚奉公に出る。
普通丁稚の年季は15年と言われるが、博はわずか9年で年季が開け、別家が許された。
そして、1892年(明治25年)1月15日、丸尾花子と結婚。独立開業への準備を始めたのだった。

森下博の生誕地(鞆の浦と仙酔島)

大阪の商家修行時代の森下博
(明治17年 15歳)

森下博夫妻と長女次子(明治34年)

森下南陽堂創業前の計算帳
(明治24年 8月吉日)
創業当時 - 森下南陽堂の発足
1893年(明治26年)2月11日、当社は薬種商「森下南陽堂」として、大阪市東区淡路町(現・中央区)に、その産声をあげた。
創業者・森下博は当時弱冠25歳。前年に結婚したばかりの妻・花子と2名の従業員というささやかな船出であった。当時の薬種商の仕事は富山や新潟などの売薬業者に原料を販売するのがひとつ。また、製薬業者へ原料を供給し、「手直し料」と称する精製の手間賃を前払いする形で資金的な援助をする役割も担っていた。
創業にあたって、森下博は事業の基本方針として次の3ヶ条を掲げた。
原料の精選を生命とし、優良品の製造販売
進みては、外貨の獲得を実現し、
広告による薫化益世を使命とする
これは創業100年を数えた今日でも「厳選された良質な素材で、優れた製品を提供し、地球的視野に立ったグローバルなフィールドで事業を展開。そして、生活者の心に響くより良い方法で人々にお届けする」という「JINTAN創業理念」として生き続けている。
しかし、理想に燃えて事業に乗り出した森下南陽堂も創業当初は決して順風満帆というわけではなかった。1896年(明治29年)2月11日には、日清戦争の功労者に贈られた金鵄(きんし)勲章にちなんだ、香袋「金鵄麝香」を発売。1898年(明治31年)には内服美容剤「肉体美白丸」を発売。いずれも時代を先取りした新しいカラーを盛り込んだ意欲的で優れた製品だったが、販売の実績だけをとれば「失敗だった」と言わざるを得ないだろう。
思うに委せぬまま苦しんだ森下南陽堂の救世主となったのが、1900年(明治33年)2月11日に世に送り出した梅毒新剤「毒滅」である。「毒滅」の処方は笹川三男三医学博士の開発。商標にはドイツの宰相ビスマルクを使用し、森下博は家財の一切を広告費につぎ込んで、日刊紙各紙に全面広告を出し、全国の街角の掲示板にポスターを出すなど、大々的な宣伝を行った。
当時、梅毒は花柳病、文明病としてその猛威を振るっており、「毒滅」は画期的な新薬として注目された。ビスマルクの「毒滅」、ビスマルクの「森下南陽堂」の名は瞬く間に広まったのである。「毒滅」の成功で森下南陽堂の業績はようやく軌道に乗り始めた。
また森下博は、対処薬としての「毒滅」に先だって、フランスから輸入したルーデサック「やまと衣」を性病予防器具として発売し、「病気は予防するものである」という考えを実践した。
これは、今日の予防医学の考え方を先取りするもので、予防や衛生が軽視されていた時代背景を考えれば画期的なことであった。

森下南陽堂創業当時の森下博
(明治26年 25歳)

森下南陽堂時代の森下博と幹部店員
(明治26~37年)

「毒滅」の広告(大阪朝日新聞)
(明治38年7月21日)

福島広告場に掲出した「毒滅」広告(明治40年)
「仁丹」誕生 - 約110年のロングセラー
現在発売されている「銀粒仁丹」の前身にあたる「赤大粒仁丹」が世に出たのは、日露戦争最大の難所とされた旅順要塞陥落のニュースに日本中が沸き返っていた、1905年(明治38年)2月11日のことであった。「毒滅」の成功で従業員も増え、資金的にも余裕ができた森下南陽堂は、新しい総合保健薬「仁丹」の開発に着手、1902年(明治35年)8月25日には店舗も手狭になった淡路町から東区道修町1丁目(現・中央区)へと移した。
総合保健薬のアイデアは森下南陽堂が開業して間もない1895年(明治28年)、台湾に出征した森下博が、現地で常用されていた丸薬からヒントを得たものだった。当時の日本の医療の状況は、今日とは比べものにならないくらいに貧しく、風邪や食あたりといった病気でも命を落とす人が少なくなかった。そこで、森下博は、台湾で見た丸薬のように万病に効果があって飲みやすく、しかも携帯・保存に便利な薬を作れないかと考えたのである。
そのアイデアはずっと暖められ続け、「仁丹」という名前が商標として登録されたのは「毒滅」発売の年の1900年(明治33年)であった。
道修町に店舗を移した森下博は、自ら処方に乗りだす一方で、その当時の薬学の権威であった千葉薬專(現・千葉大学)の三輪徳寛、井上善次郎両博士に協力を求め、研究をすすめた。また、丸薬の本場・富山に赴き、生産方法も学んだ。
処方を完成し、生産の目処もできた森下博は、さらに、丸薬の携帯性・保存性を高めるために、表面をベンガラでコーティングすることを発案した。
「赤大粒仁丹」のいわれはそこにあるが、当社のコーティング技術は、まさにこの時からスタートしたと言ってよいだろう。
仁丹の販売方式も当時としてはユニークなものであった。また、全国の薬店に突き出し屋根看板や幟、自動販売機などを設置し、新聞の全面広告を連続して出すなどの広告戦略で、薬店をサポートする旨を明示したのである。
その結果、仁丹は発売わずか2年で売薬の中での売上高第1位を達成したのである。
※本ページの「仁丹」の効能は、現行の製品のものではなく、当社の歴史に基づいて記載しております。

仁丹創売当時の自動販売機
(岐阜県神岡町高原郷土館所蔵)

仁丹創売当時の看板(道頓堀)

仁丹創売当時の1粒出しケース
(明治38年)
大礼服マークの登場 - 商標、ネーミングの由来
仁丹のトレードマークである「大礼服マーク」の由来についてはさまざまな説がある。 社長であった森下泰は生前の祖父から聞いた話として大礼服マークの由来をこう語っている。
「少年時代に祖父に大礼服の軍人さんは誰なのかと尋ねると、祖父は、あれは軍人さんじゃないと笑っていた。あれは外交官だと言うのです。つまり、仁丹は薬の外交官だということです」
仁丹の創製にあたって、森下博は総合保健薬・仁丹の効能を日本中に、さらには中国をはじめとして広く世界の人々の健康のために役立てたいと考えたのである。そして、仁丹に、健康や保健を世界に運ぶ外交官の姿を重ね合わせたのだった。
そもそも「仁丹」というネーミングも中国大陸への輸出を念頭に、東洋道徳の根本であり、「仁儀礼智信」の五常首字であり、儒教の中心で、最高の徳で、中国では文字の王とされる「仁」に、台湾でヒントを得た丸薬に使われていた「丹」の文字を組み合わせ、漢学者の藤沢南岳や朝日新聞論説委員だった西村天囚のアドバイスで「じんたん」という読みを振ったものである。のちに、中国大陸での仁丹販売に成功した森下博は「これでようやく恩返しができた」と周囲に語ったという。
仁丹創製のヒントをもらい、さらに仁丹製造のための良質の原料を提供してもらっている中国大陸の人々に良薬・仁丹を届けることができたことを心から喜んでの発言であったろう。
さて、外交官というイメージがまとまったのちも、数百回におよぶ改作と修正がなされて、トレードマークは決められていった。完成した、大礼服の帽子をかぶり、カイゼル髭をたくわえ、謹厳でりりしい中にも親しみのある表情のマークはたちまちに大衆の支持を受けた。
積極的な広告戦略とも相まって、大礼服マークは全国津々浦々に浸透し、また、世界各国に広がって「保健の外交官」という役割を積極的に果たしたのであった。
その後、大礼服マークには時代時代に合わせた細かい変更が加えられ、勲章を少なくしたり、英文字を入れたりして、現在のシンプルなデザインになった。 そして、昔からの仁丹ファンはもとより、大礼服を知らない若い世代にも、「闘牛士スタイル」として親しまれているのである。
※本ページの「仁丹」の効能は、現行の製品のものではなく、当社の歴史に基づいて記載しております。

一新堂看板製作所(大正7年)

大正元年頃の店頭看板

東京河田盛弘舎のイルミネーション
(大正元年)