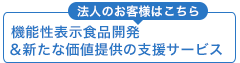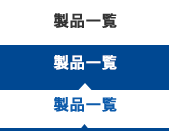森下仁丹百年物語
第2章 躍進期
世界に雄飛 - 海外進出の成功
今日、「仁丹」の名前は世界各国に知られ、中には口中清涼剤の代名詞のようにして使われている国もあるほど。「健康の外交官」として世界中から愛される仁丹の海外輸出の歴史は、発売からわずか2年後の1907年(明治40年)のことであった。
2月に森下博薬房は輸出部を設置。さらに、東京都中央区日本橋元大工町に東京倉庫を開設した。現在の東京オフィスの始まりである。輸出部は各国で「仁丹」の商標登録を行うと同時に、海外市場開拓の手始めに、中国での販売拠点づくりの準備にとりかかった。当時、考案されたのが通信委託販売である。販売を委託した先に仁丹を送りつけるシステムで、委託先としては信用がおけて、通信輸送の便が良いということから、現地の郵便代弁処(郵便局)が選ばれた。
1908年(明治41年)中国全土4000ヵ所の郵便代弁処に仁丹と宣伝ビラを小包で送り、委託販売を依頼した。さらに、これと前後して、天津、漢口、上海に出張所を開設し、社員を派遣した。
同年、大阪市東区玉堀町(現・中央区玉造)に三千坪の敷地面積を持つ第一製薬場が完成。生産体制も大陸での仁丹販売に対応できるものになった。
宣伝活動も国内に負けないくらい積極的に行った。都市部では新聞広告や辻広告などを繰り返して出し、地方や奥地では音楽隊とのぼりと旗を掲げた行進で人を集め無料サンプルを配ってまわった。大正時代のはじめ頃には中国大陸での販売は国内をしのぐ勢いにまでなった。
続いて1911年(明治44年)には、インド・ボンベイの貿易商チャウバル商会と代理店契約を交わし、翌年、同商会との提携でボンベイ支店を開設。インドでの本格的な仁丹販売を開始した。インドでも大規模な宣伝活動が行われ、日の丸を知らないインド人でも仁丹は知っているといわれるまでになり、大正半ばには代理店50、販売店5千を数え、中国と並ぶ市場を築き上げることに成功。1915年(大正4年)には、ジャワ島スマラン大博覧会への出品を機に、スマラン市にジャワ支店(インドネシア)を開設。同年、ハワイにハワイ支店を開設。南米チリでは首都バルパライソ市の邦人経営の太平洋貿易株式会社を代理店とし、南米全土への拡張を図った。
さらに、仁丹はタイ、フィリピン、シンガポール、マレーシア、エチオピア、モンバサ、ウガンダなどにも輸出された。

インド仁丹拡張運動
(大正11年4月 インド・アムリッサ市)

仁丹須知
(会社案内 大正10年1月発行)

インド・ボンベイ仁丹公司
(明治45年)

天津仁丹公司
(大正5年)
仁丹体温計の誕生 - 大衆の保健医療への寄与
森下博薬房は1922年(大正11年)森下博営業所と改称。主力商品の仁丹に継ぐ商品として「仁丹体温計」を発売した。
これは、梅毒薬「毒滅」の処方を依頼してからの旧知であった笹川三男三医学博士を社長に、前年設立された赤線検温器株式会社(現・テルモ株式会社)に出資して、販売を引き受けるというもので、森下博は取締役相談役として同社経営にも協力することになった。
第一次世界大戦後、ヨーロッパの体温計、ことにそれまで日本市場を抑えていたドイツ製品の入手が困難になり、医師の間では優秀な国産体温計の必要性を訴える声が強くなっていた。赤線検温器はこの要請に応えて、重鎮・北里柴三郎博士をはじめとする日本医学界の肝煎りで設立されたのだった。設立趣意書には「優良品の製造供給により国民保健の一助とし、且つ国家経済上に実益を挙んことを所期するものなり」とある。
当時、森下博の頭にあったのは、「保健医療」の考えであった。当時の医学の進歩と医師の増加は著しいものがあったが、十分な治療を受けられるのは依然として一部の富裕階級に限られていた。森下博は、体温計の普及によって国民大衆の保健医療に寄与できると考えたのであった。笹川博士の要請に応えて森下は「体温計というものは、われわれは病気のときしか使わないけれども、人間のあるかぎり、また病気というものがあるかぎり必要なものである」と応諾したという。
当初、仁丹の体温計は業界からは「売薬屋の体温計」と揶揄され、販売は思うように伸びなかった。しかし、森下博営業所は品質管理を徹底し、また、全国の著名人8万3千人に直接商品を送りつけて不要な場合は返品してもらうというダイレクトセールスなどを行って次第に業績をあげていった。
また、「健康は口から」という口腔衛生の考えから「仁丹ハミガキ」を発売したのも1922年(大正11年)である。容器にアルミを用いたのは、わが国のアルミ容器の先駆けでもあった。
こうして、総合保健薬の「仁丹」、保健医療の「仁丹体温計」、口腔衛生・口腔保健の「仁丹ハミガキ」が出そろい、多角化・分社経営の基盤ができた森下博営業所は、大衆の保健を広範囲に担う企業へと、大きく前進することになったのである。
※本ページ中の「仁丹」の効能は、現行の製品のものではなく、当社の歴史に基づいて記載しております。

仁丹平型体温計
(大正15年 2円30銭)

「仁丹ハミガキ」の店頭ポスター

「仁丹ハミガキ」
(大正14年頃 12銭)
大恐慌を乗り越えて - 新商品の発売と、大宣伝
赤大粒仁丹の発売以来、国内販売の拡張と海外市場開拓などによって順調に売上を伸ばしてきた仁丹であったが、昭和になると大きな危機に見舞われることになった。
1929年(昭和4年)10月24日にニューヨークのウォール街で起きた株の大暴落(暗黒の木曜日)の余波が日本にも押し寄せて、経済は深刻な恐慌に見舞われたのだった。さらに、中国大陸やジャワなどでは日貨排斥(日本商品のボイコット)運動が盛んになっていた。1932年(昭和7年)内外両面の苦境の中、森下博は、事業を仁丹に集中することで難局の打開を図ることにした。
具体的には、(1)携帯性と時代性を強調した新容器として「満州容器」(定価30銭)を発売する。(2)臨時特売を行う。(3)全国の主要販売店に直接訪問して売り込みを行う。(4)このキャンペーンのために、30余名の中堅社員を各課より動員する。(5)宣伝は、新聞2ページ広告を5大紙に50回掲載し、主要都市では旗行列と見本配布を行う、などが実行に移された。こうして、仁丹は不況に打ち克つことができたのである。

東区北久太郎町の本店営業所
(大正末頃)

「赤小粒仁丹」
(昭和2年発売 55粒入50銭)
戦時下の仁丹 - 戦災による壊滅的打撃
1937年(昭和12年)7月7日、中国華北で起きた日本陸軍と中国軍の衝突(蘆溝橋事件)に端を発し、日本は日華事変からさらに第二次世界大戦へと続く8年にも及ぶ戦時体制に突入することになった。事変当初は戦勝気分、軍需景気に沸いた日本国内も、戦火の拡大とともに次第に逼迫したものとなり、民需産業から軍需産業への移行や国民経済の締め付けが進められるようになった。
医薬品は国民の保健に欠かせないものとして、物資の統制が強化される中でも比較的自由に製造販売でき、広告についても規制が緩やかだったが、それでも当社の宣伝広告活動は1937年(昭和12年)をピークに縮小を余儀なくされた。
広告の縮小にもかかわらず、仁丹の売上高は順調に推移した。戦場では万能の護身薬として愛用され、度重なる日貨排斥にもかかわらず輸出も好調だった。仁丹は外国でも日常生活に欠かせないものになっていた。1942年(昭和17年)の仁丹の生産実績は1千300万円を超え医薬品業界のトップになった。
こうして「不況にも非常時にも強い仁丹」とまで言われた当社であったが、まもなく大きな打撃を受けることになる。
1945年(昭和20年)になるとアメリカ軍は日本の主要都市への空襲を本格化させた。東京、名古屋、大阪、神戸、北九州などはB29の空爆によって壊滅的な被害を被ったのである。当社も5月25日に東京拡張部と仁丹体温計の本社工場を全焼。さらに、7月24日の大阪市街地の大空襲で、本社と第一工場を全焼。8月14日の空襲では、第三工場を失った。
8月15日に終戦を迎えたとき、当社に残された施設はわずかに、京都府相楽郡 瓶原(みかのはら)村(現・加茂町)の第二工場のみであった。海外店はすべて接収・閉鎖され、仁丹市場の6割を占めていた中国大陸・東南アジアの市場も失われてしまった。原料の輸入も途絶して、仁丹製造再開はめどがつかない状態であった。

吉野神宮へ神旗を奉納する博と泰
(昭和16年 3月31日)

大阪女子青年国民勤労報国隊作業開始式
(昭和18年5月17日)

戦災前の本社と第一工場
(昭和20年7月の空襲で全焼)